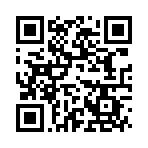2006年04月05日
フライやり始めとニンフ
今年は、まだ、ドライフライで一尾も釣っていません。
釣ったのは全てニンフです。
ニンフの釣りも、なかなか、面白く、今年はなんとなく、ニンフの出番が増えそうな気がします。
餌釣りから、フライをやり始めた頃というのは、「ドライフライなんぞに魚がでるものか」と思っていました。 続きを読む
釣ったのは全てニンフです。
ニンフの釣りも、なかなか、面白く、今年はなんとなく、ニンフの出番が増えそうな気がします。
餌釣りから、フライをやり始めた頃というのは、「ドライフライなんぞに魚がでるものか」と思っていました。 続きを読む
2006年02月17日
解禁当初
全国的に3月1日から渓流釣りが解禁となり、わくわく、そわそわしている人も多いのではないかと思います。
日差しはどことなく暖かいけれど、まだ、寒い時期、渓魚は川底にへばりついていることが多いものです。
一般的に、フライフィッシングは、落差の少ない、里川での釣りとなり、落差の多い山岳渓流は、もう少し暖かくなってからなのですが、私は、餌釣りで賑わっている山岳渓流へ行きます。
餌釣りならば、この解禁当初というのは、ビギナーの方でも簡単に釣れると言われていますが、フライフィッシングは、逆に、そうは、簡単ではありません。
魚は、ほとんど流れのない淵の底にへばりついていているからです。
続きを読む
日差しはどことなく暖かいけれど、まだ、寒い時期、渓魚は川底にへばりついていることが多いものです。
一般的に、フライフィッシングは、落差の少ない、里川での釣りとなり、落差の多い山岳渓流は、もう少し暖かくなってからなのですが、私は、餌釣りで賑わっている山岳渓流へ行きます。
餌釣りならば、この解禁当初というのは、ビギナーの方でも簡単に釣れると言われていますが、フライフィッシングは、逆に、そうは、簡単ではありません。
魚は、ほとんど流れのない淵の底にへばりついていているからです。
続きを読む
2006年01月20日
魚、釣りについて
水面から水中というのは見えません。
竿を介し、水中あるいは水面へ糸を介すと、水中を想像し魚が針にかかる姿を想像します。
どこからともなく、魚は出てきて魚は針を加え、糸に伝わり、竿へ伝わり、手に伝わり、水中を必死で泳ぐ魚を、実感と、焦燥感を伴って想像します。
しかし、その水中の様子を竿を握っていれば見ることができません。
水中の様子を映像ではなく、魚が針をくわえて力走する様子を実際に目を通してつぶさに見ることができたら、どんなに素晴らしいだろうかと思います。
もう、既に昔、二十年ぐらい前、知り合いの人はある沢に入り、釣りをしても、毒でも流したんではないかと思うほど、魚が釣れなかったそうです。
そこは、ヤマトイワナの生息域で、放流はされていません。
多分、釣りきられて居なくなってしまったのか、魚が居ない沢なんだろうと、その時は考えたそうです。
しかし近年そこの沢へは、いつ行っても半日釣れば、10尾~20尾は釣れます。
私は7~8年程前に、そこは釣れると聞いて、毎年その沢へ行っています。
最初の頃は、二十五センチ以上のサイズばかりが釣れ、イワナの楽園と言っていた程です。(本当は釣り人の楽園)最近では、知る人ぞ知るという感じになった為か、サイズが小さいものが多くなりました。
沢自体に水量がそんなにある訳ではないので、釣り人が入り、持ち帰れば魚は小さくなり、減っていくでしょう。
でも、二十年くらい前、これと同じ事が起こっていたとすれば、数多く釣れるから、多くの釣り人が入り、魚が減り、一時期人が入らなくなり、近年に至り残っていた魚がすくすくと成長し魚が増えたと、単純に考えてしまいます。
それとも、ただ単に、その二十年前、魚がたまたま釣れなかっただけなのかもしれません。
そこの沢は、両岸の上に林道がついていず、植林もほとんどされていない原生林に近い状態で、餌も豊富で、魚にとって居心地の良い環境ですので、魚が居なくなるとは考えにくい環境です。
色々と想像しますが、水の中の出来事は想像を超えているなという思いがします。
魚が釣れないと、この川は魚が居ない、放流すれば魚が増えるだろうと安易に考えてしまいます。
でも、魚を放流すれば、人為が加わってしまいます。
本来イワナの生息域なのに、下流にイワナ、上流にヤマメ(アマゴ)だけというような、本来であればおかしなことがあります。
また、本来はヤマトイワナしかいないはずの川に、日光イワナがいたりと。
何か、むやみに放流のし過ぎなのではないかと思えてきます。
キャッチ&リリース区間がありますが、放流して、キャッチ&リリース区間に設定しても、在来の魚を守る、増やすという意味においては、成り立っていないような気がします。
何もしないで、キャッチ&リリース区間にするというのが、在来の魚を守るという意味においては、一番良いような気もしますが、釣った魚を食べるという楽しみをもった人もいますから、そこら辺は、より多くの魚を釣る為にできることを、魚に愛着をもち、個人個人が釣りを楽しめば、きっと、管理なんかしなくても、良い釣り場ができるような気がします。。
そうなって欲しいです
竿を介し、水中あるいは水面へ糸を介すと、水中を想像し魚が針にかかる姿を想像します。
どこからともなく、魚は出てきて魚は針を加え、糸に伝わり、竿へ伝わり、手に伝わり、水中を必死で泳ぐ魚を、実感と、焦燥感を伴って想像します。
しかし、その水中の様子を竿を握っていれば見ることができません。
水中の様子を映像ではなく、魚が針をくわえて力走する様子を実際に目を通してつぶさに見ることができたら、どんなに素晴らしいだろうかと思います。
もう、既に昔、二十年ぐらい前、知り合いの人はある沢に入り、釣りをしても、毒でも流したんではないかと思うほど、魚が釣れなかったそうです。
そこは、ヤマトイワナの生息域で、放流はされていません。
多分、釣りきられて居なくなってしまったのか、魚が居ない沢なんだろうと、その時は考えたそうです。
しかし近年そこの沢へは、いつ行っても半日釣れば、10尾~20尾は釣れます。
私は7~8年程前に、そこは釣れると聞いて、毎年その沢へ行っています。
最初の頃は、二十五センチ以上のサイズばかりが釣れ、イワナの楽園と言っていた程です。(本当は釣り人の楽園)最近では、知る人ぞ知るという感じになった為か、サイズが小さいものが多くなりました。
沢自体に水量がそんなにある訳ではないので、釣り人が入り、持ち帰れば魚は小さくなり、減っていくでしょう。
でも、二十年くらい前、これと同じ事が起こっていたとすれば、数多く釣れるから、多くの釣り人が入り、魚が減り、一時期人が入らなくなり、近年に至り残っていた魚がすくすくと成長し魚が増えたと、単純に考えてしまいます。
それとも、ただ単に、その二十年前、魚がたまたま釣れなかっただけなのかもしれません。
そこの沢は、両岸の上に林道がついていず、植林もほとんどされていない原生林に近い状態で、餌も豊富で、魚にとって居心地の良い環境ですので、魚が居なくなるとは考えにくい環境です。
色々と想像しますが、水の中の出来事は想像を超えているなという思いがします。
魚が釣れないと、この川は魚が居ない、放流すれば魚が増えるだろうと安易に考えてしまいます。
でも、魚を放流すれば、人為が加わってしまいます。
本来イワナの生息域なのに、下流にイワナ、上流にヤマメ(アマゴ)だけというような、本来であればおかしなことがあります。
また、本来はヤマトイワナしかいないはずの川に、日光イワナがいたりと。
何か、むやみに放流のし過ぎなのではないかと思えてきます。
キャッチ&リリース区間がありますが、放流して、キャッチ&リリース区間に設定しても、在来の魚を守る、増やすという意味においては、成り立っていないような気がします。
何もしないで、キャッチ&リリース区間にするというのが、在来の魚を守るという意味においては、一番良いような気もしますが、釣った魚を食べるという楽しみをもった人もいますから、そこら辺は、より多くの魚を釣る為にできることを、魚に愛着をもち、個人個人が釣りを楽しめば、きっと、管理なんかしなくても、良い釣り場ができるような気がします。。
そうなって欲しいです
2005年12月25日
釣りについて
釣りっていうものは、釣れなければ面白くありません。
しかし、だからといって、釣れすぎても面白くありません。
釣りを始めた頃っていうのは、釣れないから何とか魚を釣ってやろうと、躍起になるものです。
試行錯誤を繰り返し、それが、徐々に釣れだし、釣れるようになります。
一旦魚が釣れだすと、今度は、もっと、数を多く釣りたいという欲がでてきます。
ある程度、数が釣れると、数が釣れるのは面白くなくなり、今度は、大物が釣りたくなります。
自分の思い描いていた、大物が釣れると、今度は、他の釣法を試してみたくなります。
そこで、釣りへのこだわりが始まり、「釣れれば良いっていうものじゃあない」ということになります。
ロッドへのこだわりや、魚種へのこだわり、場所へのこだわり、釣法へのこだわりということになります。
段々、釣り方を変えていき、新たな釣り方への挑戦をし続けていく限り、ずっと、楽しめるのが釣りです。
フライフィッシングという釣り方は、特にそれが面白く、キャスティングの面白さ、釣れた時にラインを引く面白さ、フライを作るタイイングの面白さなどがあります。
キャスティングといっても、魚のいるポイントに入れるだけでは駄目で、状況によって、ラインを曲げたりして、ポイントまで入れたり、左手は常にラインを操作しなければなりません。
状況によって、対応するテクニックをこなすだけでも、面白く、さらに、思い描いたとおりに魚が反応してくれれば、なおさら、面白くあります。
さらには、魚が捕食している餌に対応させるための、マッチ・ザ・ハッチの釣りなどで、ユスリカなど、極小のミッジを作ったり、投げ入れたりするのも、さらに、釣りを難しくさせてくれます。
フライフィッシング一つとっても、色々な釣り方があるので、そこには、水面下のニンフしかやらないという人や、ウエットしかやらないとか、様々な、それぞれ趣向性のこだわりが存在します。
その趣向性のために、フライフィッシングってなにやら難しそう、と思い描く人もいるかと思います。
ですが、フライフィッシングっていうのは、別に決まりもなく、キャスティングも上手く出来なくたって、フライがどんなものであろうと、釣れる魚は釣れます。
でも、やっていくと、今まで釣れていた魚が、はたりと、釣れなくなったりする事があり、そこで、試行錯誤をして、自分なりの釣り方を見つけると、安定して釣れるようになります。
安定しだすと、面白みが半減するので、それぞれのこだわりが、存在して、簡単ではないが、それによって、釣れたことの面白みが増大していきます。
釣りというのは、同じ釣法でも、一人、一人、違った方法論をもっていて、どれもが、釣れる方法です。
「釣りに絶対はない」
なんて言われ方をしますが、釣りというのは、個人が、個人なりの愉しみ方をもって、釣れても釣れなくても、没頭出来るのが魅力的だと思います。
様々なフライ用品を紹介していると、様々なこだわりがあり、特に最近、このように思う今日この頃です。

しかし、だからといって、釣れすぎても面白くありません。
釣りを始めた頃っていうのは、釣れないから何とか魚を釣ってやろうと、躍起になるものです。
試行錯誤を繰り返し、それが、徐々に釣れだし、釣れるようになります。
一旦魚が釣れだすと、今度は、もっと、数を多く釣りたいという欲がでてきます。
ある程度、数が釣れると、数が釣れるのは面白くなくなり、今度は、大物が釣りたくなります。
自分の思い描いていた、大物が釣れると、今度は、他の釣法を試してみたくなります。
そこで、釣りへのこだわりが始まり、「釣れれば良いっていうものじゃあない」ということになります。
ロッドへのこだわりや、魚種へのこだわり、場所へのこだわり、釣法へのこだわりということになります。
段々、釣り方を変えていき、新たな釣り方への挑戦をし続けていく限り、ずっと、楽しめるのが釣りです。
フライフィッシングという釣り方は、特にそれが面白く、キャスティングの面白さ、釣れた時にラインを引く面白さ、フライを作るタイイングの面白さなどがあります。
キャスティングといっても、魚のいるポイントに入れるだけでは駄目で、状況によって、ラインを曲げたりして、ポイントまで入れたり、左手は常にラインを操作しなければなりません。
状況によって、対応するテクニックをこなすだけでも、面白く、さらに、思い描いたとおりに魚が反応してくれれば、なおさら、面白くあります。
さらには、魚が捕食している餌に対応させるための、マッチ・ザ・ハッチの釣りなどで、ユスリカなど、極小のミッジを作ったり、投げ入れたりするのも、さらに、釣りを難しくさせてくれます。
フライフィッシング一つとっても、色々な釣り方があるので、そこには、水面下のニンフしかやらないという人や、ウエットしかやらないとか、様々な、それぞれ趣向性のこだわりが存在します。
その趣向性のために、フライフィッシングってなにやら難しそう、と思い描く人もいるかと思います。
ですが、フライフィッシングっていうのは、別に決まりもなく、キャスティングも上手く出来なくたって、フライがどんなものであろうと、釣れる魚は釣れます。
でも、やっていくと、今まで釣れていた魚が、はたりと、釣れなくなったりする事があり、そこで、試行錯誤をして、自分なりの釣り方を見つけると、安定して釣れるようになります。
安定しだすと、面白みが半減するので、それぞれのこだわりが、存在して、簡単ではないが、それによって、釣れたことの面白みが増大していきます。
釣りというのは、同じ釣法でも、一人、一人、違った方法論をもっていて、どれもが、釣れる方法です。
「釣りに絶対はない」
なんて言われ方をしますが、釣りというのは、個人が、個人なりの愉しみ方をもって、釣れても釣れなくても、没頭出来るのが魅力的だと思います。
様々なフライ用品を紹介していると、様々なこだわりがあり、特に最近、このように思う今日この頃です。
2005年12月18日
天井を突き破れば
今日は寒いです。
こんな寒い日は、暖房の効いたぬくぬく暖かい部屋で、ごろごろしていたいものです。
暖房の効いた部屋にいると、つい、起きているのだか寝ているのだか分からない状態に陥ってしまい、ほわほわとした湯気のような、霧のようなものが、広がってきます。
白い、ぼんやりとした、湯気のようなところからは、揺らめく黒い影がぼんやりと見えます。
ぼんやりと黒い影をみていると、視界が一瞬、真っ暗になり、真っ青な光できらめく海が見えます。
波立ち、きらめき、穏やかな海が、眼下に広がっています。
しばらく眺めていると、風が吹き、ゆらっと体勢が崩れます。
海が近づいてきます。
いままで広がっていた海が、絞り込まれ、さらに、絞り込まれていくうちに、目の前が真っ暗になります。
それも、束の間辺りは、明るくなり、目を開けると天井が見えます。
天井は、次第にくるくると回り、渦を巻き始めました。
目がくるくると回り始めます。
体は、渦の中に吸い込まれ、水の中を突き進みます。
広々とした感じをとおりぬけ、やがて、心地よい刺激を感じます。
その刺激は、徐々に強まり、圧力となり、その圧力は強くなり、体を押し戻そうとします。
さらに激しく、押し戻そうと、力士がツッパリをくりだしているような感じがします。
そんな感じが、少し変化し、さらに大きな力を感じます。
大きな力に、踏ん張りながら、きつく、きつく、力を入れました。
私は立っています。
耳に訴えかけてくる、岩にぶつかる、流れの音。大きな岩に淀む音。無数の石ころを転がす音。
どれもが絡み合って、静かなようで、大きく、鼓動を高めるような、耳に訴えかける音です。
辺りは、薄暗く、白い雪が岩の上にちょこんと乗り、緩やかなRを描く大きな淵を作り出している岩盤には、氷が下へ下へと伸びています。
淵には、水滴が何秒か一回落ち、波紋を広げています。
小さな石と、石とがこすれる音がします。
何度も。
それが、次第に大きくなり、息を吐く音が聞こえてきました。
その息は、小学生くらいの、子供でした。
大きくまたいで、石の上を飛び越えています。
その、子供は私の方に近づいてきて、私の目の前で立ち止まりました。
私は声をかけました。
「何をしているんだい」
でも、声は空気に振動しないで、辺りに響きません。
私の頭の中だけで消化されるようです。
子供は目の前の大きな岩や流れの先を見ています。
そして、私のことなど気にもとめず、川原の中央にある、石をちょこんと飛び移り、対岸へわたり、また、上流へ向かっていきました。
そういえば、学校帰り、沢をよく、上がりました。
どこまで、上流にいけるか。
運動靴で、川から、ひょっこり顔をだしている石を渡り、大きな岩をよじ登り。
この季節ならではの、遊びです。
時に小さな石の上から滑り、川へ落ちてびしょ濡れになったこともあります。
そんな時親に怒られて、もう川へ遊びに行ってはいけないと、川遊び禁止令が言い渡されました。
しかし、こんな、面白い遊びは止められるはずもなく、またもや、川へ遊びにいきました。
部屋の中で、上を見上げると、天井を突き破り空が見えます。
空は、地上を鏡にして、水を映し出し、地上の様子を映し出してくれるでしょう。
それは、時に過去だったり、未来だったりします。

こんな寒い日は、暖房の効いたぬくぬく暖かい部屋で、ごろごろしていたいものです。
暖房の効いた部屋にいると、つい、起きているのだか寝ているのだか分からない状態に陥ってしまい、ほわほわとした湯気のような、霧のようなものが、広がってきます。
白い、ぼんやりとした、湯気のようなところからは、揺らめく黒い影がぼんやりと見えます。
ぼんやりと黒い影をみていると、視界が一瞬、真っ暗になり、真っ青な光できらめく海が見えます。
波立ち、きらめき、穏やかな海が、眼下に広がっています。
しばらく眺めていると、風が吹き、ゆらっと体勢が崩れます。
海が近づいてきます。
いままで広がっていた海が、絞り込まれ、さらに、絞り込まれていくうちに、目の前が真っ暗になります。
それも、束の間辺りは、明るくなり、目を開けると天井が見えます。
天井は、次第にくるくると回り、渦を巻き始めました。
目がくるくると回り始めます。
体は、渦の中に吸い込まれ、水の中を突き進みます。
広々とした感じをとおりぬけ、やがて、心地よい刺激を感じます。
その刺激は、徐々に強まり、圧力となり、その圧力は強くなり、体を押し戻そうとします。
さらに激しく、押し戻そうと、力士がツッパリをくりだしているような感じがします。
そんな感じが、少し変化し、さらに大きな力を感じます。
大きな力に、踏ん張りながら、きつく、きつく、力を入れました。
私は立っています。
耳に訴えかけてくる、岩にぶつかる、流れの音。大きな岩に淀む音。無数の石ころを転がす音。
どれもが絡み合って、静かなようで、大きく、鼓動を高めるような、耳に訴えかける音です。
辺りは、薄暗く、白い雪が岩の上にちょこんと乗り、緩やかなRを描く大きな淵を作り出している岩盤には、氷が下へ下へと伸びています。
淵には、水滴が何秒か一回落ち、波紋を広げています。
小さな石と、石とがこすれる音がします。
何度も。
それが、次第に大きくなり、息を吐く音が聞こえてきました。
その息は、小学生くらいの、子供でした。
大きくまたいで、石の上を飛び越えています。
その、子供は私の方に近づいてきて、私の目の前で立ち止まりました。
私は声をかけました。
「何をしているんだい」
でも、声は空気に振動しないで、辺りに響きません。
私の頭の中だけで消化されるようです。
子供は目の前の大きな岩や流れの先を見ています。
そして、私のことなど気にもとめず、川原の中央にある、石をちょこんと飛び移り、対岸へわたり、また、上流へ向かっていきました。
そういえば、学校帰り、沢をよく、上がりました。
どこまで、上流にいけるか。
運動靴で、川から、ひょっこり顔をだしている石を渡り、大きな岩をよじ登り。
この季節ならではの、遊びです。
時に小さな石の上から滑り、川へ落ちてびしょ濡れになったこともあります。
そんな時親に怒られて、もう川へ遊びに行ってはいけないと、川遊び禁止令が言い渡されました。
しかし、こんな、面白い遊びは止められるはずもなく、またもや、川へ遊びにいきました。
部屋の中で、上を見上げると、天井を突き破り空が見えます。
空は、地上を鏡にして、水を映し出し、地上の様子を映し出してくれるでしょう。
それは、時に過去だったり、未来だったりします。